ビジネスやマーケティングにおいて、戦略の方向性を決定づける大きな判断材料が、「ブルーオーシャン戦略」か「レッドオーシャン戦略」かという選択です。これらは、単なるマーケティング用語ではなく、事業の成否を分ける根本的な考え方でもあります。もちろん、ECでも同じことが言えます。

ECにおいても、EC店舗開発や新規商品開発の際に議論になることがあります。
レッドオーシャンとは
レッドオーシャンとは、すでに多くの競合が存在する成熟市場のこと。ここでは「差別化」や「価格競争」が不可避となり、まさに“血で血を洗う”戦場。既存の需要を奪い合う形になるため、勝ち残るには高い戦略性や強いブランド力、優れたオペレーションが必要です。
ただし、レッドオーシャンには「すでに需要がある」という大きなメリットがあります。ユーザーの購買意欲が明確で、市場も可視化されているため、的確なポジショニングができれば成功の可能性も高いです。資金力や運用能力に自信がある企業にとっては、あえてレッドオーシャンに飛び込むという選択肢も十分に「あり」でしょう。
ブルーオーシャンとは
一方、ブルーオーシャンは、まだ誰も注目していない、もしくは十分に掘り起こされていない市場です。競合がほぼ存在しないため、自社独自のポジションを築きやすく、高い利益率を狙うことも可能です。新しい価値を提案することで市場そのものを創造するというアプローチは、AppleやAirbnb、Uberなどの成功事例に見られるように、爆発的な成長をもたらすことがあります。
しかし、ブルーオーシャンには「本当にニーズがあるのか?」という不確実性がつきものです。市場教育が必要なケースも多く、短期的な収益化が難しいことも。また、成功すれば必ず模倣されるリスクもあるため、常に次の一手を準備しておく必要があります。
レッドオーシャンのメリットとデメリット
レッドオーシャンには明確な「メリット」と「デメリット」があります。以下にわかりやすく整理してお伝えします。
レッドオーシャンのメリット
需要が明確で市場規模が見えている
既に多くのプレイヤーが参入しているため、市場の需要や消費者ニーズがはっきりしており、リサーチや戦略立案がしやすいです。成功モデルも多数存在します。
すでにインフラや流通が整っている
販路やマーケティング手法、販売チャネルなどが確立されているため、自社がそれに乗っかる形で比較的スムーズに展開できます。
短期的な収益化が可能
競合との比較を通じて、顧客の獲得や売上の拡大が比較的早く見込めるため、キャッシュフローが安定しやすいです。
データが豊富で戦略を立てやすい
競合分析や市場調査がしやすく、価格帯、ターゲット層、商品設計などの根拠が取りやすいです。
❌ レッドオーシャンのデメリット
競争が激しく、価格競争に巻き込まれやすい
他社との差別化が難しいため、価格で勝負するケースが多くなり、利益率が下がるリスクがあります。
ブランド力や資本力が必要
強いプレイヤーが多いため、資金や知名度、マーケティング力が弱いと埋もれてしまいがちです。
イノベーションが起きにくい
既存の枠組みにとらわれやすく、新しいアイデアや商品が受け入れられにくい傾向があります。
消耗戦になりやすく、長期的には疲弊する
シェア争いが常に続き、広告費や営業コストが膨らみやすく、リソースが消耗されやすいです。
🔍 まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | ・市場が明確 ・参入の障壁が低い ・短期収益化が可能 |
| デメリット | ・競争が激化 ・価格競争に陥る ・利益率が下がる |
ブルーオーシャンのメリットとデメリット
ブルーオーシャンのメリット
競合がほとんどいない
未開拓の市場をターゲットにするため、差別化の必要が少なく、「価格競争」に巻き込まれるリスクも低めです。
独自の価値を提供できる
新しい発想やサービスで市場を創造するため、自社の強みをそのまま武器にできます。ブランドの独自性が築きやすいです。
高利益が期待できる
競争が少ないうちは価格主導権を握りやすく、利益率の高いビジネス展開が可能です。プレミアム路線も実現しやすいです。
リーダー的ポジションを築ける
最初に市場を切り開いた企業は、その分野の“パイオニア”として認知されやすく、信頼やブランド力も高まりやすいです。
ブルーオーシャンのデメリット
市場が未成熟で需要が読みにくい
「そもそも需要があるのか?」という不確実性が常につきまとうため、リスクが大きいです。
市場教育に時間とコストがかかる
新しい概念や価値を顧客に理解してもらうまでに時間がかかるため、短期的な成果が出にくい傾向があります。
模倣されやすい
ブルーオーシャンが注目されると、すぐに他社が参入してきて、結局レッドオーシャン化してしまう可能性があります。
失敗した時のダメージが大きい
前例のない挑戦となるため、失敗のリスクが高く、事業撤退や投資回収が難しくなる可能性があります。
🔍 まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | ・競争が少ない ・独自価値を提供できる ・高利益が狙える ・パイオニアになれる |
| デメリット | ・需要が読みにくい ・教育コストがかかる ・模倣されやすい ・失敗リスクが高い |
レッドオーシャンとブルーオーシャンが適しているケースと事例
ブルーオーシャンとレッドオーシャンは、企業の「状況」や「目指すゴール」によって選ぶべき戦略が異なります。それぞれが「有効に機能するケース」と「実際の事例」をセットで紹介します。
🟥 レッドオーシャンが適しているケースと事例
✅ 【こんな場合に向いている】
- 大手企業や資本力のある企業
- 既存市場で差別化可能な強みがある(コスパ、スピード、ブランド力など)
- 成長よりも安定性・効率を重視したい
- 短期間で利益を上げたい
💡事例
■ ユニクロ(ファストファッション)
アパレル業界は激戦区ですが、「高品質 × 低価格 × 大量生産」という明確なポジションで勝ち抜きました。効率化されたオペレーションと店舗展開でレッドオーシャンでも収益性を保っています。
■ マクドナルド
飲食業界という超レッドオーシャンの中で、ブランド力・価格競争力・店舗数などの「資本と仕組み」で差別化。安定した集客力を維持しています。
■ ドラッグストア業界(例:スギ薬局、ウエルシア)
どこも似た商品を扱う業界ですが、ポイント制度や地域密着型の戦略、調剤併設などの差別化でシェアを獲得しています。
🟦 ブルーオーシャンが適しているケースと事例
ブルーオーシャンはこんな場合に向いている
- 競争の激しい市場に疲弊している
- 斬新なアイデアや独自の技術・価値を持っている
- 資金力はそこまで強くないが、スピード感と柔軟性がある
- ターゲット層がまだ満たされていないニーズを抱えている
💡【事例】
■ Apple(iTunes + iPod)
当時、音楽業界はCD販売が主流で、違法ダウンロードが問題に。Appleは「楽曲を1曲ずつ購入できる+持ち運べる」環境を提供し、まったく新しい音楽市場(ブルーオーシャン)を創出しました。
■ Cirque du Soleil(シルク・ドゥ・ソレイユ)
従来の「サーカス」業界では、動物の調達やショーの質が限界に。そこで彼らは「大人が楽しめる芸術的サーカス」という新ジャンルを創出し、価格競争を避けて高付加価値ビジネスに成功しました。
■ クラウドファンディング(例:Makuake)
資金調達=銀行・VCという常識に風穴を開けた仕組み。出資者が製品アイデアに共感して支援するという新しい「参加型市場」を作りました。
🔁 まとめ:選び方の視点
| 観点 | ブルーオーシャン | レッドオーシャン |
|---|---|---|
| 市場の競争 | ほぼなし | 激しい |
| リスク | 高いが当たれば大きい | 比較的低め |
| 向いている企業 | スタートアップ/革新企業 | 大手/資金力のある企業 |
| 成功の鍵 | 独自性・ニーズ発掘 | 差別化・効率化・資本力 |
| 成果のスピード | 中長期的 | 短期も可能 |
「最初はブルーオーシャン、後にレッドオーシャンへ進化」するパターンは、革新的なサービスが市場を切り開き、その成功を見て競合が殺到してくる典型的な流れです。
以下に、具体的な企業・サービスの事例と、どのようにブルー→レッドへ変化したかを紹介します👇
ブルーオーシャン → レッドオーシャン へ進化した事例
状況によって「最初はブルーオーシャン、後にレッドオーシャンへ進化」するパターンもあります。
① メルカリ
▶️【ブルーオーシャン時代】
- 日本ではスマホベースのフリマアプリは未成熟で、「誰でも簡単に出品・購入できる」という体験は革新的。
- ヤフオクはPCベース・オークション形式中心だったため、ライトユーザー層には入りにくかった。
- シンプルUI・匿名配送などで一気に普及。
🔁【レッドオーシャン化】
- ラクマ(楽天)、PayPayフリマ(ヤフー)などが次々に参入。
- 出品者・購入者の獲得競争が激化。
- クーポン合戦や手数料引き下げなどの競争へ。
② Airbnb
▶️【ブルーオーシャン時代】
- 宿泊業界の「常識外」にいたサービス。一般人が空き部屋を提供するという新発想で、市場を創造。
- ホテルより安く、ユニークな体験ができると人気に。
🔁【レッドオーシャン化】
- 他のバケーションレンタルサービス(Vrbo、Booking.comなど)が類似サービスを展開。
- 規制強化や税制の変更で運営コストも増加。
- プラットフォーム内でも宿泊施設が増えすぎて競争が激化。
③ Uber
▶️【ブルーオーシャン時代】
- タクシー業界の既成概念を壊すオンデマンド配車モデル。
- スマホアプリで簡単に呼べる+料金が事前にわかるなど、ユーザー体験を革新。
🔁【レッドオーシャン化】
- 他社(Lyft、DiDiなど)が続々参入。
- さらに地域ごとの規制対応、ドライバー獲得競争も激しくなり、利益確保が困難に。
④ YouTube
▶️【ブルーオーシャン時代】
- 個人が無料で動画をアップロード&公開できるプラットフォームは画期的。
- 初期は競合も少なく、動画=テレビという時代を一変。
🔁【レッドオーシャン化】
- TikTok、Instagram Reels、Twitchなどの動画サービスが続々登場。
- 広告単価・クリエイター奪い合いなどで競争が激化。
✅ このパターンの特徴と教訓
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 初期 | 革新的なサービスで「新市場」を創出する |
| 中期 | 成功に目をつけた他社が参入し、市場が広がる |
| 後期 | 競争が激化し、差別化やコスト競争が起こる(レッド化) |
🔑 教訓
- 早く市場を押さえた者が圧倒的に有利(ファーストムーバー advantage)
- ただし、模倣される前にブランド力や独自機能で差別化し続けることが重要
- 市場がレッド化した時の「第二の柱」や「次のブルーオーシャン」をどう作るかが持続成長のカギ
このような「ブルー→レッド化」の流れは、今後も起こり続ける自然な現象です。
だからこそ「先に動いた者が勝つ」ことと、「動いたあとにどう守り、広げるか」がセットで重要なんです🔥
どちらが正解かではなく、「今の自分」に合う選択を
結論から言えば、ブルーオーシャンかレッドオーシャンか、どちらが正しいという明確な答えはありません。重要なのは、自社のリソース、ブランドのポジショニング、顧客理解、そして目指すゴールに応じて、最適な戦略を選ぶことです。
大企業であれば、強みを活かしてレッドオーシャンで勝ち残ることも可能ですし、スタートアップやスモールビジネスなら、ニッチなブルーオーシャン市場を掘り起こす方が合理的かもしれません。
「戦う場所」は戦略のすべてではありませんが、その選択が未来の姿を大きく変えることは間違いありません。今、自分がどちらの海に足を踏み入れるべきなのか。しっかりと見極めてから、一歩を踏み出しましょう。
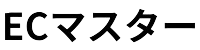



本記事の著者
フリーランス。事業会社で6年ECに従事して独立。複数のご支援に参画中。得意分野は楽天市場やYahoo!ショッピングの運営全般、広告運用、自社サイトのCRMです。経営管理修士号(兵庫県立大学大学院経営研究科)/D2Cエキスパート検定1級/日本漢字能力検定準1級。自身でもamazonを運営中。